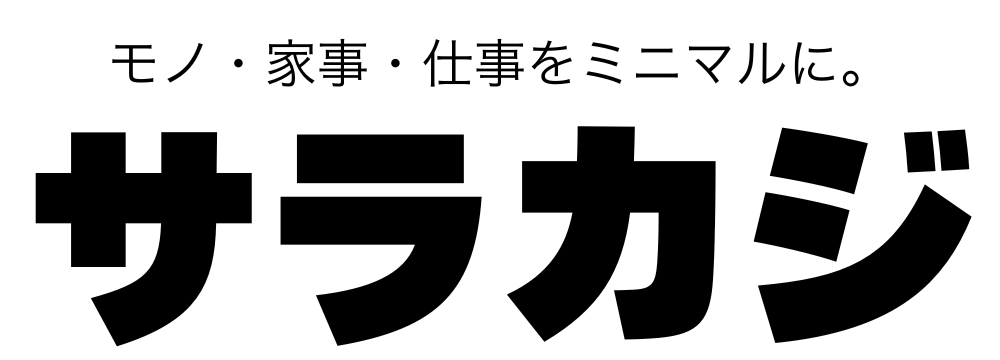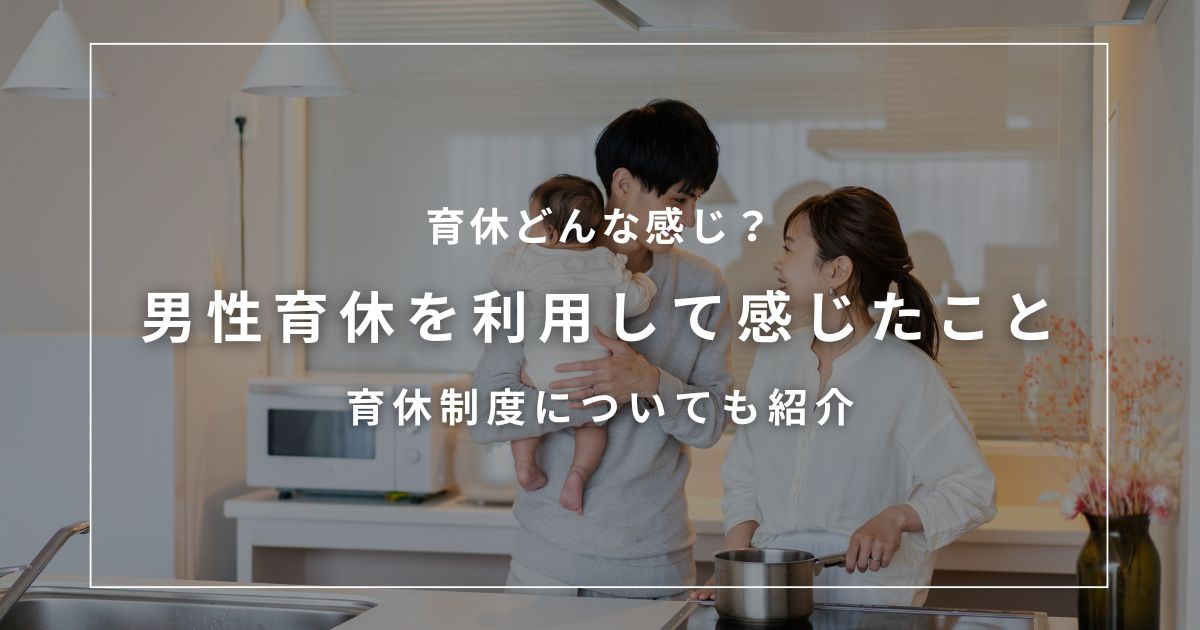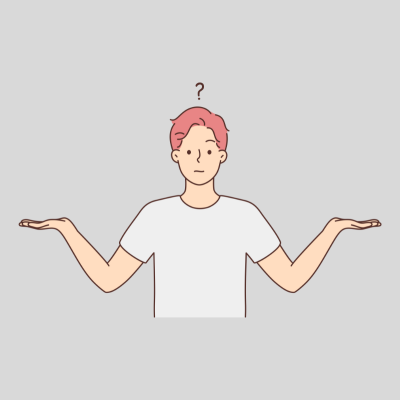 お悩み人
お悩み人育休を取るか悩んでいる。
男性の育休って、どんな感じなんだろうか?
そんな方に向けて、制度の内容やオススメの取得期間などを紹介します。
結論(男性育休について)
- 生活基盤の構築ができる。
- 妻と協力して家事・育児ができる。
- 妻の産後うつ予防になる。
- 社会保険免除制度がある。
- 税負担が軽減される。
- 妻の職場復帰の後押しになる。
- 収入が減る。
- 家でダラダラしてしまう可能性がある。
- 職場に理解がなく、取得しづらい雰囲気かもしれない。
- オススメの取得期間は1ヶ月。
- 1ヶ月であれば収入面の心配が少なく、職場復帰もしやすい。
- 妻(お母さん)は偉大。
- 子育てへの理解が深まった。
- 妻の負担軽減に繋がった。
- 仕事への理解が深まった。
- 仕事の業務効率化に繋がった。
「男性の育休」について話題になることが多くなった昨今。
育休の取得について検討されている男性も、多くなってきているかと思います。
私自身、子供が産まれた際に1ヶ月育休を取得し、家事・育児に励んだ経験がありまして。
当記事では、育休の制度や取得してみて感じたことなどを紹介します。
- 育休とは?
- 育休中の収入はどうなる?
- 子供が1歳を超えたらどうなる?
- 育児休暇との違い
- 育休のメリット・デメリット
- オススメの取得期間は?
- 育休制度を利用して感じたこと
育休とは?
育休(育児休業)とは?


育休は「育児休業」の略であり、厚生労働省のホームページにおいて、以下のように記載されています。
育児休業とは、原則1歳未満のこどもを養育するための休業で、育児・介護休業法という法律に定められています。
育児休業の申出は、それにより一定期間労働者の労務提供義務を消滅させる意思表示です。
もし、お勤め先の就業規則に育児休業に関する規定がなくても、
法律に基づき育児休業を取得することができ、会社側は休業の申し出を拒めません。
厚生労働省HPより引用
要約すると、「1歳未満の子供を育てるために取得できる休業」となります。
なお、子どもが1歳に達しても保育園が見つからないなどのやむを得ない理由がある場合は、最長2年まで延長することが可能となっています。
また、育児休業は国が法律で定めた公的制度であり、労働者の権利です。
ただ、雇用期間などにより取得可否が変わってくるので、詳しくは厚生労働省のHP等でご確認ください。
「制度について調べたけど、良く分からない。」といった方は、就業先で相談してみるのもいいかもしれません。
育休中の収入はどうなる?


育休中の賃金支払いについての規定はないため、休業中に賃金を支払うか否かは事業主の裁量に委ねられているのが現状。
その代わり、育休中には育児休業給付金が給付されます。
育児休業給付金とは、育児休業を取得した際に受け取ることができる給付金のことです。
育休中の収入の減少を補うことで安心して育児に専念できるよう、国が支援する制度となっています。
具体的には、雇用保険の被保険者であることを条件に、育児休業前の月額賃金の約67%が給付されます。
なお、181日以降は約50%に引き下げられます。
また、令和7年4月から制度変更があり、最大28日間は約80%の給付となるようです。
子供が1歳を超えたらどうなる?
原則として育休は、1歳未満の子供を育てる場合にのみ使用できます。
しかし、子どもが1歳に達しても保育園が見つからないなどのやむを得ない理由がある場合は、最長2年まで延長することが可能となっています。
2歳以降は育休を取得できないため、時短勤務など、各企業が設けている制度を利用することになるかと思います。
育児休暇との違いは?
育児休暇は、従業員の育児のための「休暇」のことです。
育児休業が労働者の権利である一方、育児休暇は事業主が独自に設置する制度となります。
ですので、育児休暇の対象者・期間・給付金等については、企業によって異なります。
育休のメリット


- 生活基盤の構築ができる。
- 妻と協力して家事・育児ができる。
- 妻の産後うつ予防になる。
- 社会保険免除制度がある。
- 税負担が軽減される。
- 妻の職場復帰の後押しになる。
生活基盤の構築ができる


子育てをするには、色々な基盤作りが必要。
子育ての生活基盤例
- 本などで子育ての勉強
- ベビーベッドの設置
- ベビー湯おけや哺乳瓶などの準備
- 車へのチャイルドシートの取り付け
仕事をしていると基盤作りの時間は限られてしまいますし、「あっ、あれ準備できてなかった!」といった形で慌てることも。
育休を取得すれば、お母さんと赤ちゃんが退院するまでの間に生活基盤を構築することができます。
特に一人目のお子さんの場合は、この準備期間のある・なしで全然変わってきますよ。
妻と協力して家事・育児ができる


育休最大のメリットが、妻と協力して家事・育児ができることだと思っています。
というのも、出産による体力低下や頻繁な授乳により、お母さんは体力を消耗するもの。
そんな時こそ、夫の出番。
料理や掃除などの家事や、寝かしつけ、夜泣きの抱っこなどを担当することで、妻側の負担を軽減することができます。
妻の産後うつ予防になる


女性は産後、ホルモンバランスの乱れや育児負担が重なり、産後うつになりやすいと言われています。
ですので、夫婦で助け合いながら育児に取り組み、妻の家事・育児負担を軽減することで、妻の産後うつの予防に繋がります。
社会保険免除制度がある
育休中は、厚生年金保険料や健康保険料などの社会保険料の免除制度があるので安心。
なお、これらの保険料の負担額は、所属している健康保険組合によって異なります。
税負担が軽減される


育児休業給付金は非課税なので、育休の翌年度は所得税と住民税の負担が軽減されることに。
結果として、育休中でも休業前の手取り月収の約8割ほどがカバーされることになります。
妻の職場復帰の後押しになる
夫が育休を取れば、妻の職場復帰がしやすくなるケースも。
例えば子供が産まれた際は妻が育休を取得し、生後半年で妻が育休から復帰する一方、夫が育休を取得するといった具合です。
これまでは育児の負担が妻側に偏ることが多くあり、妻が職場に復帰できないといったケースもあったようです。
しかし、夫と分担して育児をすることで、妻の職場復帰に繋がると思います。
育休のデメリット


- 収入が減る。
- 家でダラダラしてしまう可能性がある。
- 職場に理解がなく、取得しづらい雰囲気かもしれない。
収入が減る
育休を取得する際、特に気になってしまうのが収入面。
育休中は育児休業前の月額賃金の約67%(181日以降は約50%)にとどまるため、どうしても収入減は避けられません。
ただ、社会保険料の免除や税負担の軽減がありますし、半年までであればそこまで収入減とはならないかなと思います。
家でダラダラしてしまうかもしれない


育休で最も避けなければならないことが、育休を取得したのにダラダラしてしまうこと。
これでは妻のサポートどころか、逆にイライラさせてしまうことになりかねません。
当たり前の話ですが、育休は夫の休暇ではありません。育児のために取得するものです。
育休を取得するのであれば、「家族のために家事・育児を頑張るんだ。」という認識を持った方が良いと思います。
職場によっては取得しにくい
男性の育休に理解のない職場であれば、取得がしづらいかもしれません。
ただ、育休は労働者の権利ですし、育休を取得したい旨を伝えれば良いと思います。
とはいっても、育休からの復帰後のこともありますし、できるかぎり穏便に取得したいところ。
ですので、出産よりも早い段階から職場と相談し、引き継ぎ準備などを進めていくことでスムーズな育休取得に繋がると思います。
オススメの取得期間は?
オススメの期間


私のオススメする取得期間は、1ヶ月となります。
1ヶ月をオススメする理由
- 赤ちゃんが外出できない生後1ヶ月までの間、妻と交代で育児ができる。
- 最大28日間、育児休業前の月額賃金の約80%が育児休業給付金として給付される。
- 長期の育休と比較して、職場復帰がしやすい。
1ヶ月であれば、収入が確保でき職場復帰もしやすいので、気軽に取得しやすいと思います。
取得期間の比較
| 取得期間 | 1ヶ月 | 半年 | 1年 |
|---|---|---|---|
| メリット | 賃金の約80%が給付 職場復帰しやすい | 半年間、仕事を休める 給付額が1年休業する場合より多い | 1年間、仕事を休める |
| デメリット | 1ヶ月しか休めない | 賃金の約67%給付となる ※およそ2ヶ月目以降 | 賃金の約50%給付となる ※181日以降 職場復帰しづらい |
取得期間が短いほど収入面での減額は少ないですし、職場への復帰もしやすいかと思います。
「貯金はいっぱいあるし、家事・育児に専念したい!」
といった方は、1年間育休を取得するのもありかなと思います。
赤ちゃんはいつから外出できる?


赤ちゃんとの外出は、原則として1ヶ月健診が終わってからと言われています。
というのも、産まれたばかりの赤ちゃんは、
- 体温調節がうまくできない。
- 免疫機能や抵抗力が未熟である。
- 体力が未熟である。
といった理由から、外出すべきではないからです。
ですので、夫婦で交代で外出などができるよう、1ヶ月の取得がオススメです。
育休制度を利用して感じたこと
- 妻(お母さん)は偉大。
- 子育てへの理解が深まった。
- 妻の負担軽減に繋がった。
- 仕事への理解が深まった。
- 仕事の業務効率化に繋がった。
妻(お母さん)は偉大


とにかく、妻(お母さん)は偉大だと感じました笑。
授乳は昼夜関係なしにしなければなりませんし、おむつ交換やゲップをさせる回数も多いですよね。
それなのに、料理や洗濯などの家事までしている方には頭が下がります。
「これまでに男性育休が浸透していなかったことが信じられない。」と感じたくらいです。
だからこそ、妻の負担を軽減するためにも、男性が育休を取ることに大きな意義があると思いました。
子育てへの理解が深まった


産まれたての頃から子育てに参加することで、子育ての大変さや楽しさなどを知ることができました。
仕事をしていながらだと、ここまで育児に深く関わることはできなかったと思います。
また、仕事がない分、余裕を持って育児をできたのも良かったですね。
妻の負担軽減に繋がった
育休を取得したおかげで、家事全般と育児の一部を私が担当することができ、妻の負担軽減に繋がりました。
また、産まれたての子供は四六時中気が抜けないため、二人体制で育児ができたことは大きかったです。
仕事への理解が深まった
仕事の引き継ぎをするためには、内容をきちんと理解する必要があります。
また、引き継ぎ準備をしている中で気付いたこともあり、振り返りの良い機会になりました。
仕事の業務効率化に繋がった
引き継ぎをするということは他の職員に負担がかかる訳なので、必要な仕事のみをお願いしたいところ。
そこで引き継ぎ業務を見直すと共に、分かりやすい資料作りを心がけました。
結果として、業務効率化に繋がりました。
まとめ


ここまでご覧いただき、ありがとうございました!当記事をまとめます。
- 1歳未満の子供を育てるために取得できる休業で、労働者の権利。
- 雇用期間などにより取得可否が変わってくる。
- やむを得ない理由がある場合は、最長2年まで延長することが可能。
- 2歳以降は育休を取得できないため、時短勤務など、各企業が設けている制度を利用することになる。
- 育休中は育児休業給付金が給付される。
- 育児休業が労働者の権利である一方、育児休暇は事業主が独自に設置する制度となる。
- 生活基盤の構築ができる。
- 妻と協力して家事・育児ができる。
- 妻の産後うつ予防になる。
- 社会保険免除制度がある。
- 税負担が軽減される。
- 妻の職場復帰の後押しになる。
- 収入が減る。
- 家でダラダラしてしまう可能性がある。
- 職場に理解がなく、取得しづらい雰囲気かもしれない。
- オススメの取得期間は1ヶ月。
- 1ヶ月であれば収入面の心配が少なく、職場復帰もしやすい。
- 妻(お母さん)は偉大。
- 子育てへの理解が深まった。
- 妻の負担軽減に繋がった。
- 仕事への理解が深まった。
- 仕事の業務効率化に繋がった。
育休取得の参考になれば幸いです。
お時間があれば、以下の記事もチェックしてみてください!
ベビーカーの必要性についてまとめた記事 ↓
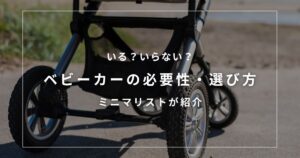
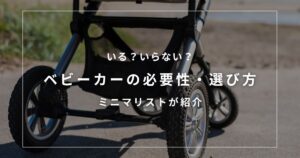
子供とのお出かけの持ち物についてまとめた記事 ↓


家事の時短術についてまとめた記事 ↓